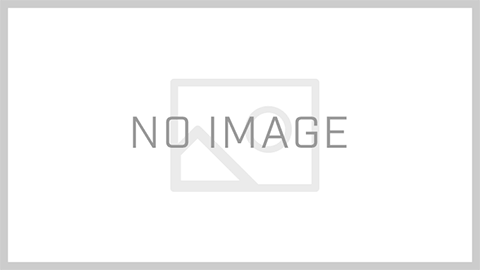1. 石炭化学工業とは
石炭化学工業とは、石炭を原料として化学製品を生産する産業の総称です。
石炭を燃料として利用するだけでなく、化学原料として分解・変換し、多様な化学品を得ることが特徴です。
その中心となる技術が「乾留(かんりゅう)」や「ガス化」です。
これによりコークス、石炭ガス、タール、ベンゼン、ナフタリン、フェノールなどが生まれ、後の化学工業の発展につながりました。
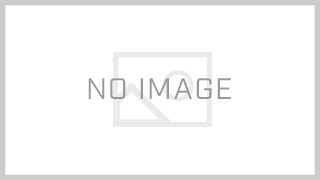
2. 起源と黎明期(18世紀〜19世紀初頭)
2.1 石炭利用の拡大
-
18世紀後半の産業革命では、蒸気機関の普及とともに石炭需要が爆発的に増加。
-
当初は燃料利用が中心だったが、鉄鋼業に必要なコークス製造の過程で化学的副産物が得られることが発見される。
2.2 コークス炉の発展
-
1760年代:イギリスでコークス炉の改良が進み、副産物として石炭ガス(照明用)、コールタール(化学原料)が得られるようになる。
-
石炭ガスは都市ガスとして、19世紀初頭のロンドンやパリで街灯照明に活用され、都市インフラを変革。
3. 成長期(19世紀中葉〜20世紀初頭)
3.1 コールタール化学の発展
-
コールタールは100種類以上の有機化合物を含む混合物。
-
1820〜1840年代:ベンゼン、トルエン、ナフタリン、フェノールなどの単離が進む。
-
1856年:英国のW.H.パーキンがコールタール由来のアニリンから世界初の合成染料「モーブ」を発明。
→ 石炭化学が合成染料工業の出発点となる。
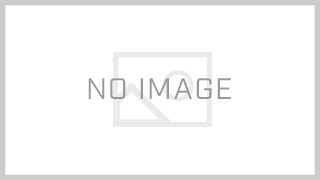
3.2 医薬・爆薬への展開
-
フェノールからは殺菌剤(クレゾール)、アスピリン原料が開発。
-
トルエンやニトロベンゼンは火薬や爆薬の原料に利用され、軍需産業とも結びつく。
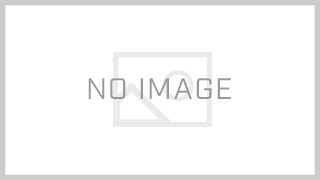
4. 全盛期(20世紀前半〜中葉)
4.1 第一次世界大戦と化学工業
-
戦時需要で爆薬、医薬、合成ゴムなど石炭化学品の需要急増。
-
ドイツは石炭資源を活用して世界最大の化学工業国となり、BASFやIGファルベンが隆盛。
4.2 液体燃料化技術の登場
-
1920〜1930年代:石炭液化法(ベルギウス法、フィッシャー=トロプシュ法)が開発され、石炭からガソリンや軽油を合成可能に。
-
原油不足の国(ドイツ、日本)で戦略的技術として注目。
5. 衰退と転換(20世紀後半)
5.1 石油化学の台頭
-
1950年代以降、安価で効率の良い石油化学が急成長。
-
ナフサクラッカーによるエチレン・プロピレン生産が主流となり、石炭化学は徐々に主役の座を失う。
5.2 石炭化学のニッチ化
-
石炭は発電用燃料としての役割が主流に。
-
一部では特殊用途(炭素繊維、活性炭、電極材)や無煙燃料の製造に利用。
6. 現代の石炭化学(21世紀)
6.1 環境負荷低減への挑戦
-
従来型石炭化学はCO₂排出が多く、地球温暖化対策の観点から縮小傾向。
-
しかし、中国やインドでは依然として石炭依存度が高く、石炭からオレフィン・メタノールを生産するCTO(Coal to Olefin)、CTM(Coal to Methanol)が拡大。
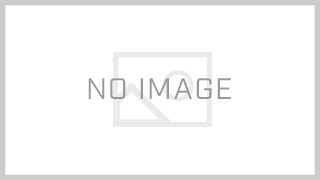
6.2 高度利用技術
-
高効率ガス化複合発電(IGCC)
-
炭素資源循環型の化学品生産(CO₂回収利用)
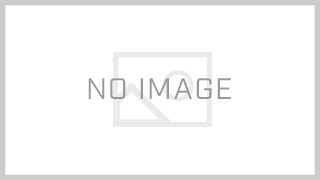
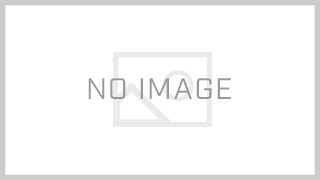
7. 石炭化学工業の歴史的意義
-
近代有機化学の出発点
合成染料・医薬品・爆薬など、多くの有機化学工業の祖。 -
エネルギーと化学の融合
燃料利用と化学品製造が一体化した産業モデル。 -
石油化学への橋渡し
プロセス技術や分離精製のノウハウが石油化学の発展に直結。
8. まとめ
石炭化学工業は、産業革命期の照明用ガスやコールタール化学から始まり、20世紀前半には世界の化学工業を牽引しました。その後、石油化学に主役を譲ったものの、現代でも一部の国・分野で重要な役割を果たしています。
この歴史を振り返ることで、化学産業の進化の道筋や、資源と技術革新の関係が見えてきます。