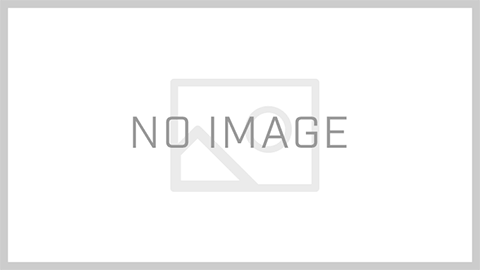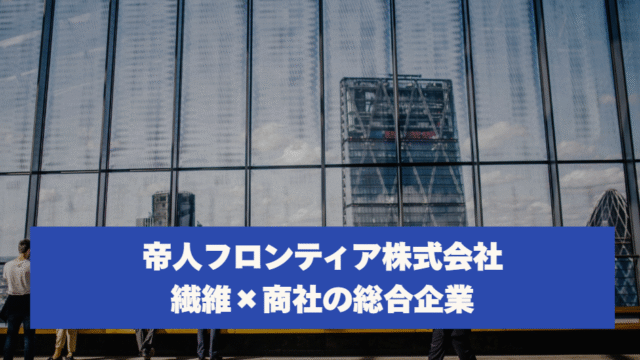1. ペロブスカイト太陽電池とは
ペロブスカイト太陽電池(perovskite-solar-cell)は、ペロブスカイト型結晶構造を持つ有機無機ハイブリッド化合物を光吸収層に用いた次世代太陽電池です。
特徴としては、軽量・柔軟・印刷製造可能であり、シリコン太陽電池では難しい用途展開が可能です。
-
変換効率:研究レベルで25%超(シリコン並み)
-
製造方法:溶液塗布、印刷法など低温プロセス
-
構造:透明電極 / ペロブスカイト層 / 電子輸送層 / ホール輸送層 / 電極
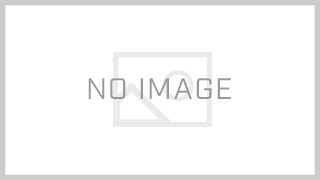
2. 積水化学工業の参入背景
積水化学は住宅用建材、プラスチック加工、高分子材料に強みを持つメーカーであり、
ペロブスカイト太陽電池の「フィルム化・長寿命化・耐候性向上」といった課題解決に自社の樹脂・フィルム技術を応用できると判断して開発に参入しました。
目標は、建物・都市全体に溶け込む発電インフラの実現です。
3. 積水化学のペロブスカイト太陽電池の特徴
3.1 フィルム型・軽量構造
-
基板に柔軟フィルムを採用
-
重さはシリコン太陽電池の約1/10
-
曲面や垂直面にも設置可能
3.2 高耐候性
-
積水の高分子封止技術で耐湿・耐熱性を確保
-
屋外での長期安定発電を目指す
3.3 大面積化技術
-
ロール・ツー・ロール印刷方式を採用し、量産化に適した工程
-
大面積セルでも変換効率の低下を抑制
4. 開発の歩み
| 年 | 主な出来事 |
|---|---|
| 2017年 | ペロブスカイト太陽電池の開発開始 |
| 2020年 | 10cm角モジュールで世界トップクラスの耐候性実証 |
| 2021年 | 屋外長期実証開始(ビル壁面・屋上で試験) |
| 2022年 | フィルム型大面積モジュール試作成功 |
| 2023年 | 大阪駅ビル壁面での実証公開、量産化目標を公表 |
| 2025年以降 | 実用化・商業展開予定 |
5. 想定用途
5.1 建材一体型太陽電池(BIPV)
-
窓ガラス、外壁パネル、屋根材と一体化
-
建物デザインを損なわずに発電
5.2 都市インフラ
-
ビル壁面・駅舎・商業施設の垂直面
-
防音壁やシェルターの表面利用
5.3 移動体・モバイル電源
-
電動車両の車体、バス停、仮設施設
-
災害時の非常用電源
6. 技術的課題と対応
| 課題 | 積水化学の対応策 |
|---|---|
| 耐候性(湿気・紫外線) | 高分子封止材・フィルム技術で保護 |
| 大面積化による効率低下 | 均一塗布・印刷技術の最適化 |
| 製造コスト | ロール・ツー・ロール大量生産方式採用 |
| 鉛使用問題 | 鉛封じ込め技術、鉛フリー材料の研究 |
7. 他社との比較(国内外)
-
国内:積水化学はフィルム型で強み、パナソニックは高効率小型セル、東芝は透明型に注力
-
海外:Oxford PV(英)はシリコンとのタンデム型、Saule Technologies(ポーランド)は印刷型量産
積水は軽量・大面積・建材一体型という差別化路線で勝負しており、既存の住宅建材事業との親和性が高い点が特徴です。
8. 将来展望
-
2025〜2030年:国内のゼロエネルギービル(ZEB)・住宅向けに普及
-
海外展開:東南アジアや欧米のBIPV市場を狙う
-
社会インフラ化:都市景観と一体化した太陽光発電網
-
環境貢献:軽量化により輸送・設置時のCO₂排出削減
9. まとめ
積水化学のペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟・高耐候性を武器に、従来のシリコン太陽電池では困難だった場所にも発電設備を広げる可能性を持っています。
同社の建材技術との融合により、「建物全体が発電する都市」の実現に近づくと期待されます。
量産化・長寿命化・環境対応の課題を乗り越えれば、住宅・商業施設・インフラのあり方を根本から変えるポテンシャルがあります。