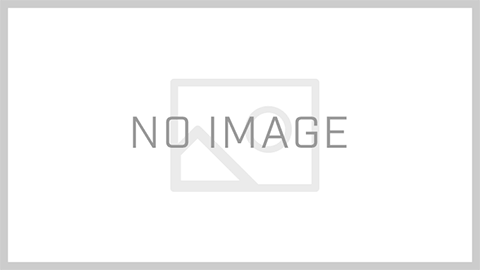1. 基本概要
フェノール(C₆H₅OH)は、芳香族炭化水素ベンゼン環に水酸基(–OH)が直接結合した化合物です。
別名「石炭酸(せきたんさん)」とも呼ばれ、無色〜白色の結晶性固体で、わずかに甘い芳香を持ちますが、空気中で酸化するとピンク〜赤褐色を帯びます。
-
分子式:C₆H₅OH
-
分子量:94.11
-
融点:約 40.5 ℃
-
沸点:約 181.7 ℃
-
溶解性:水にやや溶ける(温度上昇で溶解度増加)、有機溶媒に良く溶ける
-
酸性度(pKa):約 9.95(アルコールより酸性が強い)
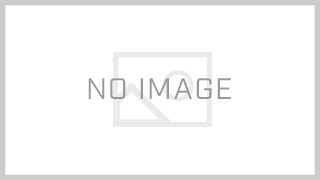
2. 歴史と発見
-
1834年:ドイツの化学者F.F.ルンゲが、石炭タールからフェノールを単離。
-
1860年代:英国の外科医ジョセフ・リスターが、フェノール溶液を手術の消毒に応用し、外科手術の無菌化に貢献(フェノール消毒法)。
-
19世紀後半〜20世紀前半:石炭乾留(コールタール)からの回収が主流。
-
現在はほとんどが石油化学プロセスで製造。
3. 性質と化学的特徴
3.1 酸性の強さ
-
フェノールはアルコール類より酸性が強いのは、ベンゼン環との共鳴構造によってフェノキシドイオン(C₆H₅O⁻)が安定化するため。
3.2 反応性
-
酸塩基反応:強塩基(NaOH)と反応してナトリウムフェノキシドを生成。
-
求電子置換反応:水酸基の電子供与性により、オルト・パラ位に置換が起こりやすい。
-
酸化反応:空気中で酸化され、着色やキノン類生成。
4. 製造方法
4.1 クメン法(現在の主流)
-
ベンゼンとプロピレンを触媒下で反応 → **クメン(イソプロピルベンゼン)**生成
-
クメンを酸化 → クメンヒドロペルオキシド
-
酸分解 → フェノールとアセトンを得る
※副産物のアセトンは溶剤や樹脂原料としても利用。
4.2 過去の製造法
-
石炭タール蒸留法(副産物回収)
-
クロロベンゼン加水分解法(Dow法)
-
ベンゼンスルホン酸アルカリ融解法
5. 主な用途
5.1 樹脂原料
-
フェノール樹脂(ベークライト):電気絶縁性・耐熱性に優れ、家電部品や自動車部材に使用。
-
ビスフェノールA(BPA):ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂の原料。
5.2 化学品中間体
-
カプリロラクタム(ナイロン6原料)
-
アジピン酸(ナイロン66原料)
-
無水フタル酸、フェノール系界面活性剤
5.3 殺菌・消毒
-
歴史的には消毒液や防腐剤に使用(現在は毒性のため制限)。
-
一部ののどスプレーやうがい薬に低濃度配合される場合あり。
6. 安全性と取り扱い
6.1 健康影響
-
強い腐食性と皮膚吸収性あり。
-
皮膚に触れると化学熱傷を起こし、中枢神経や腎臓に障害を与える恐れ。
-
吸入や摂取は急性中毒の危険性が高い。
6.2 法規制
-
日本の化学物質管理法、労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則で規制対象。
-
EUのREACH規制、米国のTSCAでも管理。
7. フェノールの現代的課題と展望
7.1 環境負荷の低減
-
製造時のCO₂排出削減技術の開発。
-
石油由来からバイオマス由来フェノールへの移行研究。
7.2 高機能材料分野での進化
-
高耐熱・高強度樹脂の原料として需要継続。
-
医薬・農薬の中間体としての応用拡大。
8. まとめ
フェノールは、石炭化学の時代から石油化学の時代まで生き残ってきた基本有機化合物であり、樹脂・繊維・医薬など幅広い分野に不可欠な原料です。
その高い反応性と汎用性は産業発展の原動力となりましたが、同時に毒性と環境負荷の管理が求められます。
今後は、環境対応型製造プロセスやバイオ由来原料化がフェノールの新たな歴史を形作るでしょう。