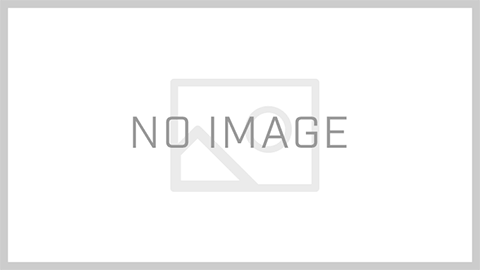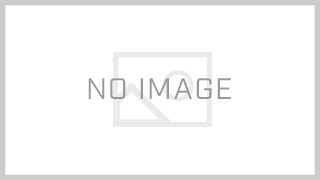1. 乾留(かんりゅう)とは
乾留(かんりゅう)とは、有機物を空気(酸素)を遮断した状態で加熱し、熱分解によって揮発成分や固体炭素を得る操作です。
特に石炭化学工業で重要な技術です。
酸素がないため燃焼は起こらず、分子構造が熱によって切断され、ガス・液体・固体に分かれます。
-
温度範囲:通常500〜1,200℃
-
目的:燃料(コークス、ガス)、化学原料(タール、ベンゼン等)、副産物の回収
2. 石炭乾留の歴史的背景
2.1 初期利用(18〜19世紀)
-
最初は木材の乾留(木炭製造)が先行して行われており、これを石炭に応用。
-
18世紀末、英国で都市ガスとして石炭ガスを供給するために乾留が本格化。
2.2 都市ガスとコールタール化学の発展
-
19世紀、石炭乾留の副産物として石炭ガス(照明用)とコールタールが注目される。
-
コールタールから染料・薬品が製造され、石炭化学工業が拡大。
3. 乾留の原理
3.1 熱分解反応
石炭を加熱すると、複雑な高分子構造が分解して揮発性成分と固体炭素に分かれます。
-
低温乾留(500〜700℃)
-
多くのタールや揮発成分を得られる
-
木炭や活性炭の製造に近い性質
-
-
高温乾留(900〜1,200℃)
-
コークス製造に適する
-
揮発成分が少なく、固体炭素率が高い
-
3.2 酸素遮断の理由
酸素があると燃焼して二酸化炭素や水になり、化学原料が失われるため。
酸素遮断により、燃やさずに成分を分離可能。
4. 乾留炉の種類
4.1 バッチ式(旧式)
-
レトルト炉
-
鉄や耐火レンガの容器に石炭を入れ、外部から加熱。
-
操作が単純だが、連続生産に向かない。
-
4.2 連続式(近代)
-
水平室式コークス炉
-
横長の炉室で石炭を加熱し、コークスを定期的に押し出す。
-
副産物回収装置と連結され、大規模製造が可能。
-
-
立て型連続炉
-
石炭が上から投入され、下に向かって徐々に加熱される。
-
5. 乾留で得られる主要製品
| 区分 | 製品名 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 固体 | コークス | 高炉の還元材、燃料 |
| 液体 | コールタール | 染料、医薬品、防腐剤、炭素材料 |
| 液体 | アンモニア水 | 肥料原料、化学品 |
| 気体 | 石炭ガス | 照明、都市ガス |
| 気体 | ベンゼン系炭化水素 | 溶剤、化学原料 |
6. 現代における乾留の位置づけ
6.1 役割の変化
-
都市ガスは天然ガスに置き換わったため、石炭ガス生産は縮小。
-
現在は主に製鉄用コークス製造が中心。
-
コールタールからの化学品生産は依然として重要。
6.2 環境対応
-
副産物回収と排ガス処理を強化
-
高効率・低公害型の乾留炉(環境負荷削減)
7. 乾留の意義
-
資源の最大活用:燃料だけでなく、化学原料としても利用可能。
-
化学工業の起点:染料・医薬・合成樹脂など近代化学を切り開いた。
-
持続可能性への再注目:バイオマス乾留やカーボンニュートラル燃料製造にも応用可能。