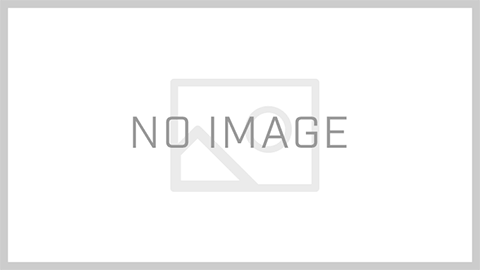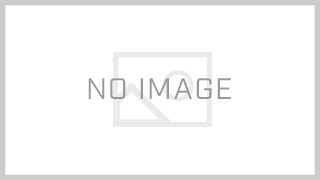1. はじめに
石炭は従来、燃料や製鉄用コークスの原料として利用されてきましたが、近年では化学原料として再び注目されています。その中でも、**CTO(Coal to Olefin)とCTM(Coal to Methanol)**は、石炭を出発原料としてオレフィン(エチレン・プロピレンなど)やメタノールを製造する技術です。
特に中国では、豊富な石炭資源と原油輸入依存の低減を目的として、この技術の商業化が急速に進んでいます。
2. CTO・CTMの定義
-
CTM(Coal to Methanol)
石炭をガス化して合成ガス(CO + H₂)に変換し、触媒反応によってメタノール(CH₃OH)を製造するプロセス。 -
CTO(Coal to Olefin)
上記CTMで得られたメタノールをさらにMTO(Methanol to Olefin)プロセスにかけ、エチレン・プロピレンなどのオレフィンに転換するプロセス。
→ CTO = Coal → Synthesis Gas → Methanol → Olefin
3. プロセスの流れ
3.1 石炭からオレフィンまでの一般的フロー
3.2 各工程の概要
(1) ガス化工程
-
高温高圧下で酸素や水蒸気を供給し、石炭をCOとH₂の混合ガスに変換。
-
不純物(硫黄、窒素化合物、粉塵)を除去。
(2) メタノール合成工程(CTM)
-
触媒(Cu-ZnO-Al₂O₃系)を用い、合成ガスをメタノールに転化。
-
反応式:CO + 2H₂ → CH₃OH
(3) MTO工程(CTO)
-
ゼオライト触媒(SAPO-34など)でメタノールを脱水・分解し、エチレンやプロピレンを生成。
-
副生成物としてC₄以上の炭化水素も得られる。
4. 技術的背景と発展の理由
4.1 資源事情
-
中国やインドなどは石炭資源が豊富で、石油・天然ガスの輸入依存が高い。
-
CTO・CTMは、国内資源活用型の化学品生産を可能にする。
4.2 石油化学との比較
-
石油化学ではナフサ分解でオレフィンを得るが、原油価格変動の影響が大きい。
-
CTOは石炭価格に依存するため、原油高の時期に競争力を持つ。
5. 利点
-
資源自立性
石油輸入依存を低減できる。 -
大量生産性
大規模プラント化が可能。 -
原料価格の安定
石炭価格は比較的変動が小さい。 -
副産物利用
硫黄化合物やCO₂の回収利用が可能。
6. 課題
-
CO₂排出量の多さ
石炭ガス化は化石燃料の中でも温室効果ガス排出量が多い。 -
初期投資の大きさ
ガス化設備、触媒、精製工程が複雑で設備コストが高い。 -
環境規制
大気汚染物質(SO₂、NOx、粉塵)の処理が必要。 -
水資源の大量消費
冷却・洗浄工程で多くの水を必要とするため、水資源の乏しい地域では課題。
7. 中国での事例
-
神華集団(Shenhua Group)
世界最大規模のCTOプラントを内モンゴルに建設。年間数百万トン規模のオレフィンを生産。 -
寧夏煤業集団
CTMを経由したポリプロピレン製造で商業化に成功。 -
中国では環境規制が強化されつつも、依然として石炭化学の中心技術として位置づけられている。
8. 将来展望
8.1 環境対応型CTO/CTM
-
CCUS技術(Carbon Capture, Utilization and Storage)との組み合わせによるCO₂削減。
-
再生可能エネルギー由来のH₂を合成ガス製造に利用し、炭素効率を向上。
8.2 国際的な動向
-
欧米では環境負荷の高さから大型CTO/CTMは少ない。
-
アジア・中東・アフリカの石炭資源国での採用可能性が高い。
9. まとめ
-
CTMは「石炭 → メタノール」、CTOは「石炭 → メタノール → オレフィン」の流れ。
-
石油化学依存からの脱却を狙う資源国にとって戦略的技術。
-
一方で、CO₂排出量の多さと環境規制対応が最大の課題。
-
将来的にはCCUSやグリーン水素と組み合わせることで、持続可能な化学原料製造プロセスへ進化する可能性がある。