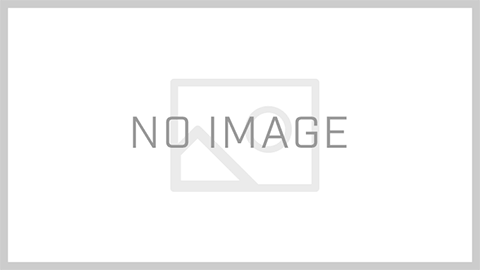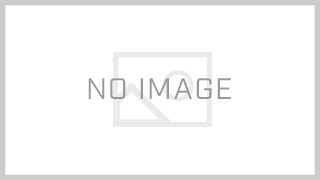1. 概要
炭素資源循環型の化学品生産とは、発電所や工場から排出される二酸化炭素(CO₂)を回収し、化学原料として再利用する技術体系のことです。
これは
CCU(Carbon Capture and Utilization)
または
CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)
の一部であり、従来は大気に放出していたCO₂を、プラスチック・燃料・化学品などの形で再資源化します。
2. 背景
-
地球温暖化対策の強化:CO₂排出量の削減は国際的課題。
-
カーボンニュートラル目標:2050年に向け、排出ゼロだけでなく循環利用が重要視。
-
化学産業の脱化石化:石油・石炭由来原料の代替としてCO₂利用が期待。
3. CO₂回収の基本プロセス
3.1 CO₂の回収源
-
火力発電所(石炭・天然ガス)
-
セメント工場
-
製鉄所
-
化学プラント(アンモニア製造など)
3.2 回収方法
-
化学吸収法(アミン溶液に吸収)
-
物理吸収法(高圧下で吸収)
-
膜分離法(特定ガスを選択透過する膜)
-
低温分離法(冷却でCO₂を液化)
4. CO₂利用の主な方法(CCU)
4.1 化学品原料化
-
ポリカーボネート:CO₂とエポキシ化合物から合成
-
ポリウレタン:CO₂由来カーボネートポリオールを利用
-
メタノール(CO₂+水素→メタノール)
-
オレフィン(メタノール経由のMTOプロセス)
4.2 燃料化
-
合成燃料(e-fuel):CO₂+グリーン水素でガソリン・軽油・ジェット燃料を合成(フィッシャー=トロプシュ法)
-
メタン化:CO₂+H₂ → CH₄(再エネガスとして利用)
4.3 無機化合物化
-
炭酸カルシウム(CaCO₃):建材・充填材
-
炭酸マグネシウム(MgCO₃):耐火材・化学原料
5. 代表的な技術例
5.1 メタノール合成(CO₂ to Methanol)
-
反応式:CO₂ + 3H₂ → CH₃OH + H₂O
-
グリーン水素(再エネ電力由来)を使用すると、カーボンニュートラル燃料・化学原料になる。
-
事例:カーボン・リサイクル・インターナショナル(CRI, アイスランド)
5.2 CO₂-ポリカーボネート
-
CO₂と酸化プロピレンを触媒反応させ、CO₂含有ポリマーを製造。
-
事例:Covestro(独)によるCO₂含有ポリオール製品
5.3 電解還元(CO₂ Electroreduction)
-
CO₂を電気化学的に還元し、ギ酸、エチレン、エタノールなどを生成。
-
再エネ電力と組み合わせることで電気で化学品を作る技術として注目。
6. 炭素循環型化学のメリット
-
CO₂削減と資源化の同時達成
廃棄ガスを化学原料に転換。 -
化石資源代替
原油・天然ガスの使用量削減。 -
新市場の創出
カーボンリサイクル製品として高付加価値化。
7. 課題
-
エネルギーコストの高さ
CO₂の化学変換には多くのエネルギーが必要(特に水素製造)。 -
経済性の確保
化石原料由来品より製造コストが高い場合が多い。 -
CO₂回収・輸送インフラの整備不足
集中型プラントから需要地への輸送網が未発達。 -
ライフサイクル評価(LCA)
全工程で本当にCO₂削減につながっているかの評価が必要。
8. 世界と日本の動向
世界
-
欧州:EUグリーンディールの一環としてCO₂利用プロジェクトを推進
-
米国:税控除制度(45Q)でCO₂利用型事業を支援
-
中国:石炭化学と組み合わせたCO₂利用(CTM/CTOとCCUSの統合)
日本
-
経済産業省が「カーボンリサイクルロードマップ」を策定
-
JERA、ENEOS、三菱ケミカルなどがCO₂由来メタノール・燃料実証中
-
東芝エネルギーシステムズがCO₂電解還元システムを開発
9. 将来展望
-
グリーン水素のコスト低下により商業化が加速。
-
再エネ+CCUによるカーボンニュートラル製造が主流化。
-
都市部の分散型プラントや、既存化学プラントの改修による導入増加。
-
バイオマス+CCUで“カーボンネガティブ”も実現可能。
10. まとめ
炭素資源循環型の化学品生産は、CO₂を環境負荷の元凶から資源へ変える技術です。
カーボンニュートラルの達成には不可欠ですが、現状ではコストとエネルギー効率が課題。
今後、グリーン水素や再エネの普及とともに、持続可能な化学産業の柱として大きく発展する可能性があります。